僕はロボット。
姿形は人間だ。
ということは正確にはアンドロイドなのだろうか。
詳しいことはわからない。
ひとつはっきりとわかっていることは、頭についているボタンを押すと僕は止まってしまう。
つまり、死んでしまうということだ。
どういう死に方をするのかはわからない。
だが、皆がその事実は知っているようだった。
自分が人間として生きていることも自覚できた。
感覚や欲は人間と同じなようだ。
頭のボタン以外はいたって『普通』に、僕は生活している。
いつ、どんな場面で死することを決断するのか
この世界では、常に核となって突きつけられている問いがある。
『いつ死ぬか』
皆が、いや僕だけなのかもしれないが、常にこの問いを自問している。
自分の生を終えるためのボタンが物理的に頭についているのだから、考えるのも当然といえば当然なのかもしれない。
寿命があるのかどうかもわからない。
ただ、ボタンを押したら死ぬという感覚だけがはっきりとある。
それに、『ボタンは自分で押すもの』という意識がはっきりとあった。
自分の死の時と場所は自分で選べる、ということだ。
『いつどんな場面で死することを決断するのか』ということが、この世界で唯一答えを出すべきことのような感覚があった。
重要な問い以外には何も疑問がない
- 頭のボタンがいつ付いたのか
- 生まれつきなのか途中からか
- ボタンを押さなくても寿命はあるのか
- ボタンを押したらどうやって死ぬのか
- 皆はどうしているのか
- そもそも自分は誰なのか
なんてことは頭に浮かんでもすぐどうでもよくなってしまう。
『いつどんな場面で死することを決断するのか』だけが考えるべきことで、決断すべきことだった。
生活もいたって『普通』だ。
妻と出掛けたり、食事をしたり、幸せに過ごしている。
決断すべきこと以外は悩むこともない、気持ちの良い日々だ。
僕の決断
ある日の夕方。
僕は妻とスーパーに自転車で向かっていた。
妻と「気持ち良いね」と自転車を漕ぎながら夕日に目を向ける。
妻が夕日に目を細めながら微笑んでいるのを見て、僕は幸せな気持ちになった。
満たされた気持ちで胸がいっぱいだった。
僕は少し自転車のスピードを落として、夕日に溶け込んでいく妻の背中を見つつ、頭のボタンに手を伸ばした。
躊躇は無かった。
僕が死ぬ場面として選んだのは、幸せななんでもないこの時間だった。
僕はボタンを押した。

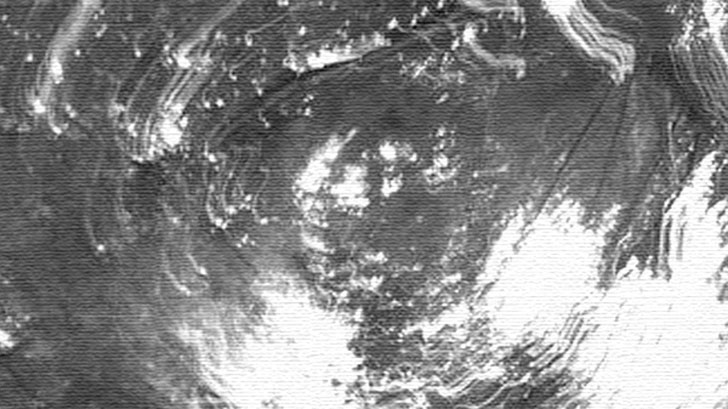
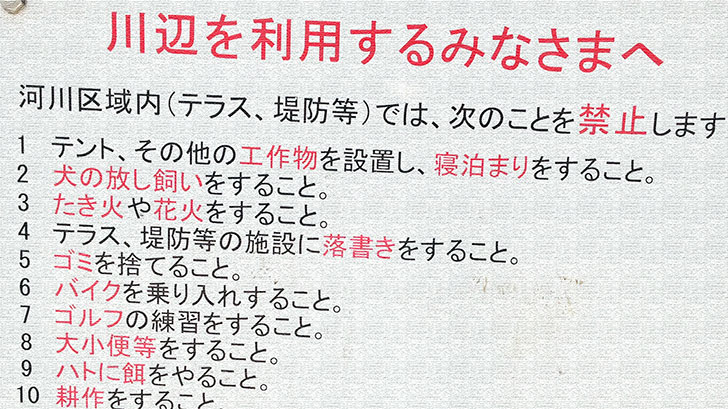

コメント