「色は混ぜれば混ぜるほど黒に近づく」
アニメ映画『バケモノの子』を観てきた。
細田守監督の作品はこれまでのどれも好きだ。
- 時をかける少女
- サマーウォーズ
- おおかみこどもの雨と雪
観ても内容を忘れてしまう映画はいくらでもあるが、全て記憶にしっかりと残っている。
『バケモノの子』についても期待を込めて映画館に足を運び、万全の席を確保して観てきた。
結果、面白かった。
やっぱり、面白かった。
登場人物は精彩を放っていて、アニメーションは緻密で動きや表情が豊かだった。
特に戦いのシーンは観ていて感動した。
身体の反応、毛の動き、物の揺れ方、アニメーターの方たちは研究を重ねたのではないかと感じた。
そういったひとつひとつの細かい動きが、躍動感となって伝わってきた。
観た後も爽快だった。
………。
けれども、
これまでの細田監督作品を観た後とは違う想いがあった。
僕はこの映画のストーリーを半年後には忘れてしまっているかもしれない。
それぞれの色は単体では綺麗だが、混ざれば混ざるほどに黒に近づく
面白かった。
けれども、
引っかかることがこの作品は多すぎた。
多すぎたため、どうしても気になってしまうが、答えは出せない。
「なんでもかんでも詰め込みすぎだ。」
そう感じている。
2時間しかない上映の中で表現できることには限りがある。
詰め込み過ぎると、
色鮮やかだったはずの表現が独立できず混ざり合って、
濁ってしまう。
『バケモノの子』が表現しようとしていたこと
物語には大抵主人公がいる。
そしてその主人公の成長が描かれる事が多い。
成長の過程には親や友人からの影響があり、その影響を与える人物の中でも重要な役割を持った人間は絞られてくる。
この作品で言えば、主人公は九太(蓮)だ。
そしてこの作品で描かれるのも九太の成長である。
では、影響を与える人物として描かれていたのは誰か。
- 熊徹(くまてつ)
- 楓(かえで)
- 一郎彦(いちろうひこ)
- 九太の父
が挙げられると思う。
そしてそれぞれが、強調した表現の象徴になっていた。
- 熊徹(くまてつ) … バケモノの象徴、バケモノと人間の絆の象徴
- 一郎彦(いちろうひこ) … バケモノの子の象徴、心の闇の象徴
- 楓(かえで) … 人間の象徴、勇気と正義の象徴
- 九太の父 … 親の象徴
序盤から中盤にかけてはバケモノの世界で九太と熊徹の絆が築かれていく過程が描かれる。
人間を弟子にしてはいけないバケモノの世界において、師弟関係ではありながら、お互いが成長していく過程が表現されていた。
この関係は最後まで続くものであり、至極わかりやすく筋の通ったものだった。
一郎彦にしても、九太との対比として描かれており、この作品の中での重要人物だ。
闇のパワーを炸裂させた一郎彦と九太の戦いが最後に描かれるのも納得出来る。
『バケモノの子』と『バケモノの子』の対決である。
一郎彦は序盤から表現されていた渋谷と渋天街の対比から見える人間界の怖さ・闇を人格化したもののようにも見えた。
人間の恐ろしい部分、『闇』の象徴として十分だったように思えた。
この二人だけでも、
- 九太と熊徹の絆とそれぞれの成長
- 人間界とバケモノ界の対比
- 『バケモノの子』が抱える悩み
- 人間の持つ『闇』
が表現されていた。
上記2人との話だけが中心であれば、この作品が表現しようとすることがもっと素直に理解できたかもしれない。
だが、ここに純粋な『人間』である2人が出現することで、熊徹と一郎彦で表現したものが明らかに濁った。
楓と九太の父だ。
楓の役割
本作のヒロインとして登場する女子高生の楓(かえで)。
このヒロインの存在が、話の筋道をあやふやにし、積み上げてきた『雰囲気』を散らしてしまった印象だった。
九太が9歳から17歳に成長するまでの過程は描かれていない。
17歳になった九太は人間界に足を踏み入れてしまう。
そこで、九太は楓に出会うのだ。
ただでさえ新たに人間界という環境が加わったにも関わらず、楓というこれまでには全くいないタイプの人物が加わったことで、観ているこちらはどの環境での気持ちで観ていれば良いのか分からなくなる。
要は、感情移入ができなくなるのだ。
彼女は図書館で騒ぐ同級生を注意するなど勇気を持った行動する人間だ。
それと同時に、本が好きで九太に勉強教えたり、取り乱した九太を宥めたりと聡明な人物として描かれている。
物語も終盤、心に闇を宿した一郎彦(いちろうひこ)と決着を着けるために九太は渋谷に戻る。
一郎彦との対戦の前、人間界での大きな存在となっていた楓を呼び出し自身の覚悟を伝える九太。
その九太の覚悟に対し、『一緒に行く』ことを決断する楓。
最後には、一郎彦の目の前に立ちはだかり、真っ当な言葉を浴びせるようなこともする。
…聡明な人間がこの決断をするだろうか。
一郎彦の狙いは九太であり、二人とも戦闘に長けているのである。
近くにいることで、役に立つどころか九太の足手まといになることは明らかだ。
この決断が起承転結の『結』部分にいまいち感情移入できない要因だった。
楓が決断した『一緒に行く』ということ。
これはストーリーの要素として、
- 九太が一郎彦と戦う(人間界を守る)意味付け
- 楓の勇気と正義の強調
を確立させるためだけのものだったのではないか。
九太が一郎彦と戦う理由としては、
- 一郎彦が九太と同じバケモノの子であること
- 熊徹の敵討ち(九太はその気持ちは無いと言っているが)
が挙げられるだろう。
だが、これだけでは人間界で戦う理由としては弱い。
そこで、楓を使った、というように見えた。
あるいは物語としてヒロインは必要と判断したのか。
真意はわからないが、存在・行動・発言すべてが他の良さを濁らせた。
九太の父の話を拒絶したときの表現の謎
人間界に頻繁に足を運ぶようになった九太は実の父親に会いに行くことにする。
実の父親は、行方知れずで九太を引き取れなかったことと警察による捜索が終わった後も探し続けていたことを九太に伝える。
そして、「一緒に暮らそう」という話を持ちかけるのだ。
だが、九太は父親が言った「つらいときのことは忘れて」という言葉に怒り、提案を拒絶する。
そしてその後、九太の心の中に闇があることが強調して表現される。
ここが引っかかった。
そもそも、その感情は闇なのだろうか?
離婚しているため会うことができず、事情があれども助けには来なかった父親に、急にこれまでのことは忘れて一緒に暮らそうと言われたのだ。
闇でも何でもなく、真っ当な怒りであり、悔しさだと思う。
誰にでも訪れる、夜のようなものだ。
夜を過ごさなければ、朝日を浴びることはできない。
それとも、そんな感情ですら闇として表現したかったのだろうか。
それですら闇というのであれば、一郎彦が闇のパワーを抱えて人間界に行ってしまったときの猪王山(いおうぜん)の後悔の念はなんなのだろう。
「?」をすっ飛ばすアニメーションが少なかった
ここまで書いてきたように、この作品では「?」となる箇所が多々あった。
だが細田守監督の作品はそういうところが多いほうだと認識している。
それでも多少の無理は問答無用で押し通し、「?」となった気持ちもアニメーションですっ飛ばしてくれる。
それが、今回は弱かった。
つじつまが合わないところを挙げていけば、きりがなくなってしまう。
それを補おうとするような多々良(たたら)と百秋坊(ひゃくしゅうぼう)のセリフ。
※大泉さんとリリーさんの声は非常に良かった
折角のアニメーションだ。
言葉なくとも伝えられた場面も多いのではないだろうか。
言葉で中途半端に伝えるから、余計に観ている側は「?」が増えるのだ。
そしてそのつじつまが合わない中でひたすら個の表現をする人物たちを、誰も傷つけないように物語は締めくくられてしまう。
まとめ
2時間という時間の中で表現するには仕方が無かったのかもしれない。
だが、それならば表現に強弱をつけて伝えたいものに重きをおくべきだ。
もしくは、どの表現もすべて大事だというのであれば、それぞれのストーリーを映画にすればいい。
序盤から中盤にかけては、カラフルな色が映える美しい表現だった。
そこに様々な色が入ってくるようになり、表現は濁って黒くなってしまい、僕の胸には届かなくなった。
僕はこの映画のストーリーを半年後には忘れてしまっているかもしれない。

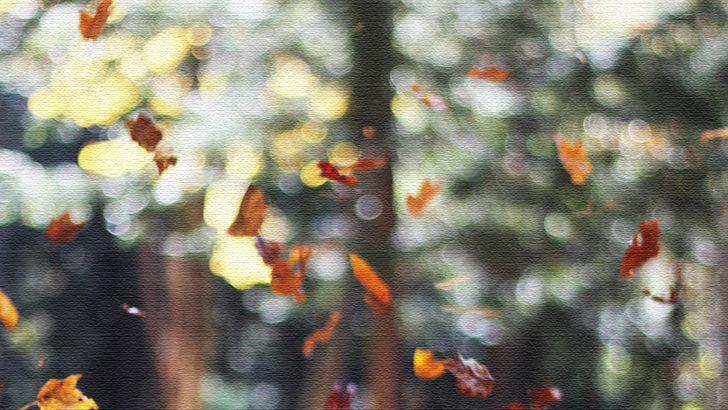


コメント